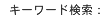|
||||||

|
|
|||||
| ホーム > 設立総会 > 基調講演:広瀬弘忠氏 | ||||||
|
災害に出合うとき 広瀬 弘忠 (東京女子大学教授) 災害を語り伝えることの大切さ
災害の記憶というものはすぐに薄れ、色あせてしまうものである。だから、忘れてしまった人の心に古い記憶をよみがえらせるために語り伝えることが大切である。 伝える様式の変遷-語り部の誕生災害の体験は、心身への非常に強い外傷体験であり、筆舌に尽くしがたい過酷な経験である。当初混乱は高ぶる感情のゆえに語ることができない人々が、次第に原体験を客体化し、自分の言葉で語り、言葉を外側にあふれさせていくことにより気持ちを整理していく。例えば広島・長崎の原爆の被爆者、沖縄戦の体験者、また阪神大震災、インド洋大津波の被災者がそうであるように、人々は固有の語りを身につけ、語りの様式を作っていくなかで、語り部が誕生する。こうして創り出された語りが、さらに進化し、普遍化したものが小説、絵画、音楽、詩といった文芸として定着する。完全に整理されたストーリーになる前段階にある語りは、素材の生の力ゆえに、かえって聞く者に鮮明な印象を与え、心に訴えるものを持つ。 “語り”と“場”の広がり
被災者が、言葉にしがたい混沌とした感情や恐怖を、被災者同士、あるいは家族の間で語り、外側にあふれさせていくとき、最初は、自分自身のための語りである。それらが、さらに友人・知人、職場の同僚といった人々へと語りの領域を広げることにより、社会的に意義を持ち始める。自分の体験を語る際には、被災当時の感情、記憶を鮮明に思い出すことになり被災者自身も自らの外傷体験を想起する厳しい状況に身をおくことになる。だが、この外傷記憶の想起に耐えることにより、次第に外傷記憶に慣れ、被災体験を整理し客観化できるようになる。 なぜ語り部が必要なのか
2005年12月に、阪神大震災の被災者に対して共同通信社が行った調査では、約9割の人が震災の体験は「かなり風化しつつある」あるいは「少し風化しつつある」と回答し、震災の風化を被災者が自覚していることが示された。また「風化させないために重要なことは」との問いに対して一番多かったのが、「語り部活動や子どもたちに震災経験を話し聞かせる等の被災者自身の活動」という回答であり、語りの重要性が指摘されている。 “語る”ことの意味 災害を語ることの効用として、語る側は、自分の悲惨な体験を整理して語ることで、それまで抑圧していた言葉に尽くせない感情や記憶、また喪失感といったものから距離をおいて客観化できると同時に、被災者のネットワーク等を通じ、防災に貢献することができる。また聞く側は、災害を追体験することにより被災者への共感や、支援の感情を持つだけでなく、自身の防災への動機づけ、さらには行動を起こすエネルギーを得ることができる。 このTeLL-Netを拡大し、世界各地の災害の被災者が一堂に会する国際会議が繰り返し開かれるならば、そこから発信される情報、体験、経験の蓄積が世界中の人々の防災に対する関心を高め、世界がさらに災害に強くなっていくための大きなステップとなると考える。 |
||||||
| ページの先頭へ | ||||||

|